サッカーチームマネジメントと会社マネジメントの共通性
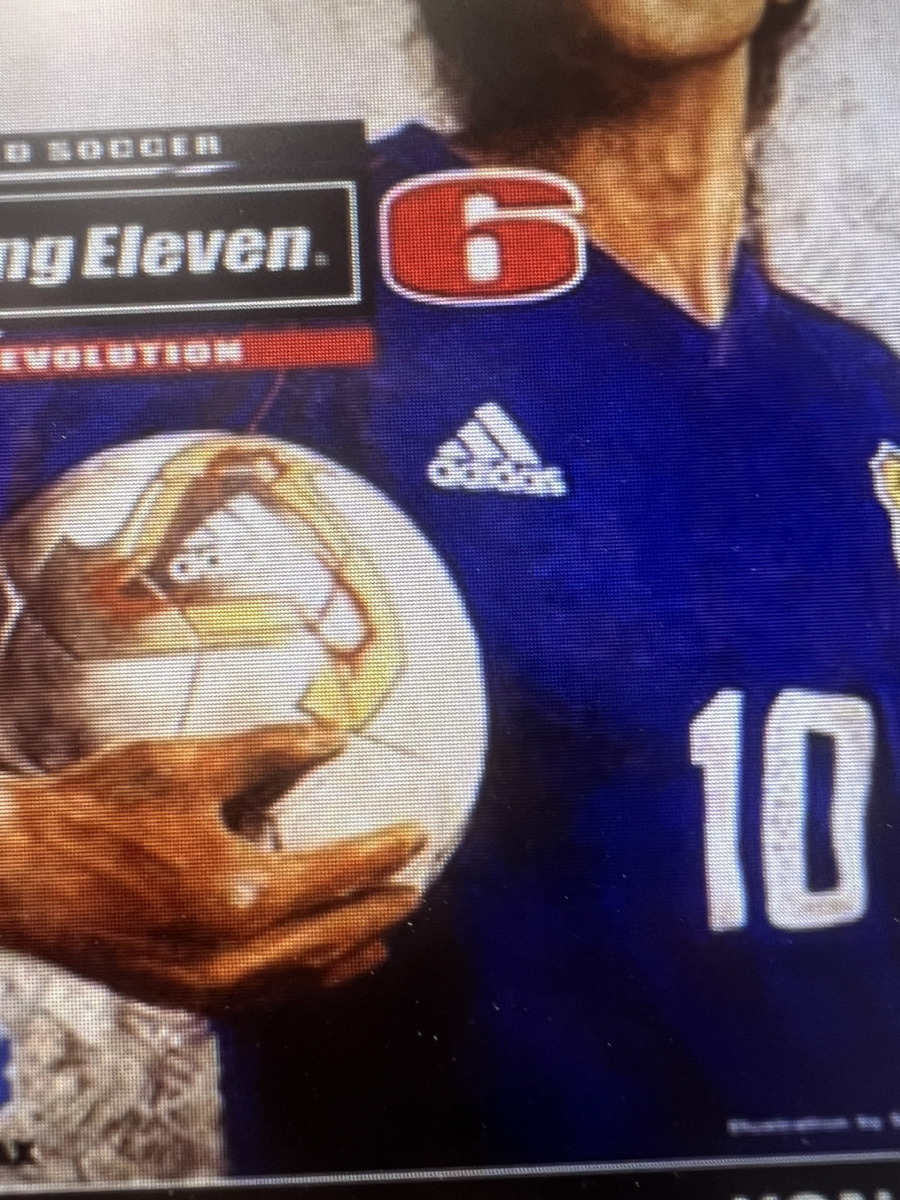
テレビゲームで経営を学んでおりました。
テレビゲームのサッカーの歴史を変えたと言われる、ウイニングイレブン。
もうこれ初期の段階からずっと大好きでやっています。
最初は、自分が好きなクラブチームを使うんです。
大体に慣れてくると、自分のクラブチームを作りたくなる。
自分のチームといっても、最初は弱小のチーム。
予算も少ないため、有名な選手を入れることができない。
平凡なチームメンバーたちを使って、1試合ずつ少しずつ勝ち進めて、ポイントを貯めていく。
ポイントがある程度貯まると、それをもとに、有名選手をクラブチームに招くことができる。
有名選手を軸に、またチームを勝ち進め、ポイントを貯めて、また有名な選手を招致する。
限られた予算の中でやるんです。
最初は少ないんですけど、少しずつ増やしていって、できることを増やしていく。
そうやって強いチームを作っていくのです。
会社経営についても、店舗経営についても全く同じです。
私は、父が経営する会社に入社し、最初に渡されたのが、自分の配属拠点の損益計算書を渡されました。
真っ赤な真っ赤な真っ赤な赤字。
集客のために何かやろうとしても、赤字が拡大するのが怖く、広告をかけられない。
新しい人を採用したいけれども、人件費が過多となり、採用をためらってしまう。
今思えば、確実に収益が上がるプランを考えて、そのための投資をすべきだったのでしょうが、当時はそこまで頭が回りません。
目の前のできることから着手していきます。
私の拠点は、スズキの販売店でした。
営業と整備の収益が、メインの収益です。
まずは黒字にすることに集中します。
黒字にするために、営業の成約率を上げるように考えました。
自分が、営業の勉強をして、それを実践して、成約率を上げていきました。
次に、販売時に付帯するオプション品の仕入れ先を変えたり、品目を増やしたりし、1取引あたりの単価を上げていきました。
すると、すぐに赤字から、トントンになりました。
次に、サービス収益を上げるために、1取引あたりの単価を上げること。
点検や車検自体を増やすために、お客様を訪問することをしていきました。自転車で回れば、社用車もいらないと考えたのです。
すると、黒字になりました。
黒字になった分、もう1人、サービスを採用しました。
採用した分、サービスの受注数を上げることができ、サービス収益を大きくすることができました、
黒字になった分、キャッシュ上多少余裕があるはずとして、少なかった在庫を増やすようにしました。
そして、今まで手をつけていなかった、広告に力を入れるようにしました。
広告といっても、チラシを作ってもお客様が来るわけではありませんでしたので、ホームページをつくりました。
月に50,000円位しか使えないと思ったので、自分で作成でき、SEO対策が可能なブログ型ホームページをつくりました。
そこに毎日投稿し、スズキでの 検索順位全国1番となりました。
来場客数が増えてきたので、1人の営業だけでは足りません。
もう1人営業マンを採用しました。
リクルートにかけるお金がもったいなかったので、友達に入ってもらいました。
今でも親友ですが、当時は喧嘩ばかりをし、結果的には彼は会社を辞めていきました。
その当時は、人を採用しては辞めてしまい、また採用しと言うものを繰り返していました。
人を採用するコスト、育成する時間コストを考えると、自分がやったほうが早いと言う思いもあったのですが、やはり、人材育成をきちんと勉強しようといたしました。
自創経営と出会ったのはこの頃ですが、最初は、1ヵ月のコンサルタントフィーが満額支払いできない旨をお伝えし、割引をしていただきました。
今でも覚えております。
神田駅のルノワール。
東川広伸先生との出会いです。
懐かしい思い出です。
それから、人の育成がだんだんとわかってきて、当初はたくさん人が辞めていましたが、人が辞めないようになりました。
逆に辞めてしまう人がいたとしても、会社の業績は伸び続けると言う結果になっております。
私がして来たことを振り返ってみると、
損益計算書を組まなく見ていた。
売り上げの1品目1品目を細かく見ていた。
原価の1品目1品目を細かく見ていた。
物件費の1品目1品目を細かく見ていた。
人件費の1品目1品目を細かく見ていた。
さして、その数値を変化させるための行動プランを立て、実践し、改善してきた。
そのため、何をどうすれば、損益計算書の数値が上がるかが分かりました。
節約型の後継者でしたので、売り上げ型の後継者に変わろうと、収益が担保できた後に、広告宣伝費への投資を行っていきました。
広告宣伝行うにも、在庫と言うものが必要となります。
在庫は、売店率が勝負となるのですが、この回転率と言うものが難しいのです。
狙った通りに売れないのです。
そこで、頭が貸借対照表へ変わりました。
損益計算書と同じく、一つ一つの科目が、何によって構成され、どのようなことをすると数字が変化するかを細かく見ていきました。
余計な資産は売り払って、手元のキャッシュをつくりました。
キャッシュが外に出るのを少なくし、手元のキャッシュが溜まるように、借入金返済の期間見直しや、減価償却費の計上についての様々な手法を用いました。
その結果、在庫資金を50,000,000円出できるということがわかり、それをもとに30台の在庫を持つようにしました。
そこから、広告を回し、集客をし、採用した人材を育成し、少しずつ収益を高めていきました。
後継者に成長するためのサークルを作っております。
そこでいつもお話しするのが、まずは損益計算書の科目の一つ一つを暗記する位覚え、その数値を変化させるためには、具体的にどのような行動やトレーニングが必要となるかー明確にする、
そして、狙った通りにその数値を作っていく。
ある程度蓄えや自信が出てきたら、新たな投資をしていく。
経営がギリギリの場合であれば、貸借対照表から入った方が良いかもしれません。
これも一つ一つ細かくです。
一つ一つの科目の数値が、具体的に何なのかを、映像として浮かぶようにしておくこと。
この辺をお話しするのです。
貸借対照表の5年後の目標。
損益計算書の5年後の目標。
その手前にある、3年の目標。
その手前にある1年目標。
(貸借対照表は別)
その前に、まずは自社の数値を把握すること。
そして、その目標を実現させるために必要となる、具体的な行動は何か、具体的なスキルは何かを考えて、後継者としての成長目標を掲げ、自分自身の人材基準を作成するというのが、最も後継者を育てるために効果的だと私は思います。
というお話でした。
そろそろ、4月以降の方針を打ち出すために、色々と考えている時期なのですが、やはり、経営者を作ること。
社長でなくても、現場の経営者、店舗の経営者。部門の経営者。
アメーバ経営では無いですが、大変な時代となりますので、数字で細かく管理をし、その数字を変化させるために、具体的な行動や必要なスキルが浮かぶ人たちを育成していくことが必要だと思います。
そういった人を育てていくというのが、ざっくりとした向こう3年間の方針となります。
と言うことを朝寝ぼけながら考えておりました。



